初めに
今回は型の最終形というべき『完全形』の微分方程式のついて学ぶ。
この型をマスターすることによって一応、1階線形微分方程式の解法は一区切りする。
『完全形』についての説明は、かなり詳しく説明したこともあって、全3回(第八回~第十回)にまとめた。長く感じるが、その分しっかりとした理解が約束される。
『完全形』の正確な定義を述べるには、いくつかの準備が必要である。この第八回では、『完全形』の定義を述べるところまで説明する。
『完全形』の微分方程式
最終目標の一般化
『一の型』、『二の型』『変数分離型』について少し復習すると、これらの微分方程式を解く上での最終目標はそれぞれ、$$\frac{d}{dx}(yの式)=f(x)・・・①$$$$\frac{d}{dx}(\mu(x)y)=f(x)・・・②$$$$\frac{d}{dx}F(y(x))=g(x)・・・③$$であったことを思い出そう。
復習が必要なら、第2回、第4回、第6回を参照すると良い。
これらの最終目標をより一般化すると、$$\frac{d}{dx}\phi(x , y)=0・・・(\ast)$$ここで、\(\phi(x , y)\) は、\(x\)、\(y\) の何らかの関数である。
上の①、②、③は全て\((\ast)\)に含まれる。実際に、①と②において、\(F(x)\) を \(f(x)\) の原始関数、すなわち$$F(x)=\int f(x)dx$$とおけば、$$①\Leftrightarrow \frac{d}{dx}\{(yの式)-F(x)\}=0$$$$②\Leftrightarrow \frac{d}{dx}\{\mu(x)y-F(x)\}=0$$と書けて、それぞれ、$$\phi(x , y)=(yの式)-F(x)$$$$\phi(x , y)=\mu(x)y-F(x)$$とおけば、\((\ast)\)の形となる。③についても同様である。
もし、与えられた微分方程式が\((\ast)\)の形に変形できたならば、$$\frac{d}{dx}\phi(x , y)=0$$の両辺を \(x\) で積分して、$$\phi(x , y)=C (C は定数)$$を得る。続く計算は、\(\phi(x , y)\) の形にもよるが、仮に\(y=(x の関数)\) の形に書けなくても、陰関数表示として解けたということになる。詳しくは後ほどやる。
長くなったが、伝えたかったことは、$$\frac{d}{dx}\phi(x , y)=0$$の形に直すことが今回の『最終目標』だということだ。
今回はこの『完全形』がどんなものかを学んでいく。ここが、1階微分方程式の解法の山場だと思って頑張ってほしい。
完全形とは?
最も一般化された1階微分方程式
はじめにどんな1階微分方程式も$$M(x , y)+N(x , y)y’=0・・・(\star)$$の形に変形できることに注意する。
どういうことか説明しよう。なんでもよいが例えば、第6回の練習問題で解いた$$e^{y}y’-x-x^{3}=0$$は$$-(x+x^{3})+e^{y}y’$$とみると、
\begin{cases}
M(x , y)=-(x+x^{3})\\
N(x , y)=e^{y}
\end{cases}として、\( (\star) \) の形になる。
このように、どんな1階微分方程式も\( (\star) \) の形に変形できるのである。
『一の型:\(y’+a(x)y=0\)』、『二の型:\(y’+a(x)y=b(x)\)』、『変数分離型:\(y’=\frac{g(x)}{f(y)}\)』もみな全て\( (\star) \) の形に変形できることのチェックはお任せしよう。
よって、\( (\star) \) は最も一般的な1階微分方程式の形であるといえるのである。
\(\frac{d}{dx}\phi(x , y)=0\)への変形手順
次の問題では、どうやって$$M(x , y)+N(x , y)y’=0・・・(\star)$$という形の微分方程式を$$\frac{d}{dx}\phi(x , y)=0$$の形に変形するかということだ。
結論から言うと、いつでもできるという訳ではなくある条件の下、変形可能である。
その条件とは何かをまず明らかにしていこう。まず、微分計算の連鎖律により、$$\frac{d}{dx}\phi(x , y)=\frac{\partial \phi}{\partial x}+\frac{\partial \phi}{\partial y}y’$$となるので、$$M(x , y)+N(x , y)y’=\frac{d}{dx}\phi(x , y)$$となるためには$$M(x , y)+N(x , y)y’=\frac{\partial \phi}{\partial x}+\frac{\partial \phi}{\partial y}y’$$つまり、
$$M(x , y)=\frac{\partial \phi}{\partial x} かつ N(x , y)=\frac{\partial \phi}{\partial y}・・・(\spadesuit)$$を満たす \(\phi(x , y)\) が存在すればよいことになる。
定理1
\((\spadesuit)\) を満たす\(\phi(x , y)\) がいつでも存在してくれるとありがたいのだが、現実はそうではなく次の条件を満たすときに限って存在する。重要な事実なので『定理』として紹介する。
\((\spadesuit)\) を満たす関数 \(\phi(x , y)\) は$$\frac{\partial M}{\partial y}=\frac{\partial N}{\partial x}$$ を満たすときに限り存在する。
この定理1は、非常に重要なのであるが、解き方のみ早急に知りたいという人は以下の証明は飛ばして次に進んでくれたらよいだろう。
まず、\((\Rightarrow)\)を示す。\((\spadesuit)\) を満たす関数 \(\phi(x , y)\) が存在するとする。仮定の第1式:\(\frac{\partial \phi}{\partial x}=M(x , y)\) から、そのような\(\phi(x , y)\) は両辺 \(x\) で積分することによって、$$\phi(x , y)=\int M(x , y)dx+h(y)・・・①$$と書ける。
ここで、\(h(y)\) は \(y\) の関数である。
次に、①の両辺を \(y\) で偏微分すると、
\begin{split}
\frac{\partial \phi}{\partial y}&=\frac{\partial}{\partial y}(\int M(x , y)dx)+h(y))\\
&=\int \frac{\partial}{\partial y}(M(x , y))dx+h'(y)\end{split}
ここで、\(M(x , y)\) は積分記号下での微分が可能であるような条件を満たしているものとする。(我々がここで取り扱う関数は大体において、問題なく可能なので過剰に気にすることはない。)
仮定の第2式から、上式の左辺は、\(N(x , y)\) となるので、$$N(x , y)=\int \frac{\partial}{\partial y}(M(x , y))dx+h'(y)$$を得る。この両辺を \(x\) で偏微分すると、\(\frac{\partial}{\partial x}h'(y)=0\)より、$$\frac{\partial N}{\partial x}=\frac{\partial M}{\partial y}$$となって結論を得る。これで、(\(\Rightarrow\)) が示された。
次に、(\(\Leftarrow\)) を示す。
逆に、$$\frac{\partial N}{\partial x}=\frac{\partial M}{\partial y}$$が成り立つとしよう。これを用いて、以下実際に、\((\spadesuit)\) を満たす関数 \(\phi(x , y)\) を構成していこう。仮定により、$$\frac{\partial N}{\partial x}-\frac{\partial M}{\partial y}=0$$すなわち、$$\frac{\partial}{\partial x}(N-\int\frac{\partial M}{\partial y}dx)=0$$が成り立つので、$$N-\int\frac{\partial M}{\partial y}dx$$は一般には \(y\) の関数である。
よって、$$g(y)=N(x , y)-\int\frac{\partial M}{\partial y}dx$$とおける。
\(g(y)\) の原始関数を \(G(y)\) とおくと、$$G(y)=\int g(y)dy=\int (N(x , y)-\int\frac{\partial M}{\partial y}dx)dy$$と書けて、これも \(y\) の関数である。
さて、次のように \(\phi(x , y)\) を構成する。$$\phi(x , y)=\int M(x , y)dx+G(y).$$すると、この \(\phi(x , y)\) は \((\spadesuit)\) を満たすのである。実際、両辺を \(x\) で偏微分すると \(\frac{\partial}{\partial x}G(y)=0\) より、$$\frac{\partial}{\partial x}\phi(x , y)=\frac{\partial}{\partial x}(\int M(x , y)dx)+\frac{\partial}{\partial x}G(y)=M(x , y).$$よって、$$\frac{\partial \phi}{\partial x}=M(x , y) は成り立つ。$$両辺を \(y\) で偏微分すると、
\begin{split}
\frac{\partial}{\partial y}\phi(x , y)&=\frac{\partial}{\partial y}(\int M(x , y)dx)+\frac{\partial}{\partial y}G(y)\\
&=\int \frac{\partial}{\partial y}M(x , y)dx+g(y)\\
&=\int \frac{\partial}{\partial y}M(x , y)dx+N(x , y)-\int \frac{\partial}{\partial y}M(x , y)\\
&=N(x , y)
\end{split}
したがって、$$\frac{\partial \phi}{\partial y}=N(x , y)$$も成り立つ。これで、(\(\Leftarrow\)) も示された。以上により定理は証明された。\(q.e.d\)
『完全形』定義
さて、これでようやく今回の目的である、『完全形』の定義を述べる準備が整った。
一般の1階微分方程式:$$M(x , y)+N(x , y)y’=0 は、$$$$\frac{\partial M}{\partial y}=\frac{\partial N}{\partial x}$$を満たすときに『完全形』の微分方程式という
上記定理1により、与えられた微分方程式が\(M(x , y)+N(x , y)y’=0\) が$$\frac{d}{dx}\phi(x , y)=0$$の形に変形できるかどうか知るためには、$$\frac{\partial M}{\partial y}=\frac{\partial N}{\partial x}$$を満たすことをチェックすればよいことが分かった!
まとめ
さて、いかがだっただろうか?
『完全形の定義』を述べるだけでも結構な準備が必要なことが分かったと思う。しかし、完全形であることのチェック自体は簡単にできるということは定理1が教えてくれた。
今回の内容をまとめると、次のようになる。
すべての1階線形微分方程式は$$M(x , y)+N(x , y)y’=0・・・①$$の形に書ける。
①が解けるためには、$$\frac{d}{dx}\phi(x , y)=0・・・②$$の形に変形されなければならない。
②の形に変形されるための必要十分条件は、$$\frac{\partial M}{\partial y}=\frac{\partial N}{\partial x}・・・③$$が成り立つことである。③が成り立つようなも微分方程式を『完全形』という。
以上が今回学んだことである。
次回の第9回は、『完全形』の微分方程式の解き方について学んでいく。
まだまだ道は長いが、コツコツ進めていくと気づけばかなりの量をこなしているものである。
ではまたディープな数学の世界で会おう!

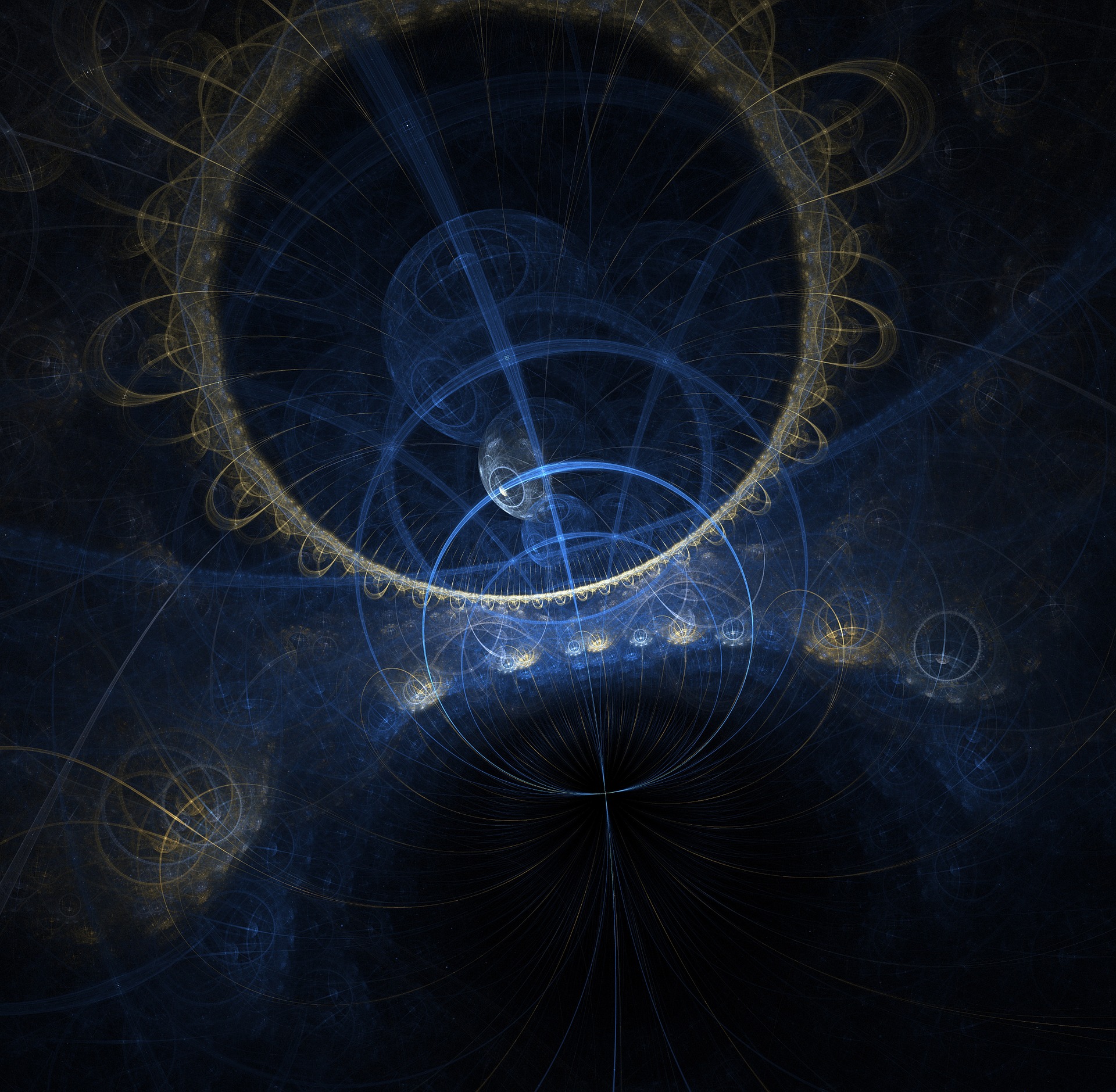


コメント